相続
━━━相続税の申告は必要か?
- 相続税は、相続などによって取得した財産の合計額から債務などの金額を控除した金額(「課税価格の合計額」)が基礎控除額を超える場合にその超える部分(「課税遺産総額」)に対して、課税されます。
- この場合、相続税の申告及び納税が必要となり、その期限は、相続にあった日の翌日から10か月以内となっています。
- 基礎控除額=(5千万円+1千万円×法定相続人の数)
- (重要)財産の中に土地が含まれる場合、例えば居住用宅地については240㎡まで80%分が減額される小規模宅地等の特例というものがありますが、この特例は、申告をしなければ適用を受けることができません。
━━━相続税はいくらかかるか?
- 相続税の計算方法は、
- ①「課税価格の合計額」を計算し、
- ②「課税遺産総額」を計算し、
- ③相続税の総額を計算し、
- ④最後に、各相続人の納付すべき相続税額を計算する、というステップを踏んで計算しますが、たいへん複雑ですので、次の表を目安にして下さい。
| 課税価格の合計額 | 1億円 | 1.5億円 | 2億円 | 5億円 |
|
各相続人の相続税の合計 |
||||
|
ケ-ス1(配偶者あり、子2人) |
200万円 100万円 |
925万円 462万円 |
1,900万円 950万円 |
11,700万円 5,850万円 |
|
ケ-ス2(配偶者なし、子2人) |
350万円 | 1,200万円 | 2,500万円 | 13,800万円 |
- 相続人が法定相続分により相続したと仮定した税額です。また、遺産分割の状況により相続税額は異なります。
- (重要)配偶者の税額は軽減(法定相続分又は1億6千万円までは税額ゼロ)されますが、この規定は申告をしなければ適用されません。
━━━申告までのスケジュ-ルは?![]()
- 相続開始後にすべきことには次のようなものがあります。
- ① 死亡届出の提出
- ② 遺言書の有無の確認と検認
- ③ 相続財産・債務の把握
- ③ 相続の放棄または限定承認の申出(3ヵ月以内)
- ④ 準確定申告(4か月以内)
- ⑤ 遺産分割協議書の作成
- ⑥ 遺産の名義変更の手続き(預金、不動産など)
- ⑦ 相続税の申告及び納付(10ヵ月以内)
- これらの順番は前後しますが、遺産分割協議が終わらなければ前には進みません。
━━━相続財産や債務を把握するためにはどうすればよいか?
- 財産や債務の中には家族が把握していないものもあるかもしれません。
- 預金などについては、金融機関からの送付書類や死亡日の残高証明書から捜すことができます。
- また、過去5年分ぐらいの預金通帳の入出金の状況を見れば、株式・国債・賃貸不動産・貸付金・借入金・保険契約などを把握することもできますし、過去の確定申告書の控えからもわかります。
- さらに、顧問税理士・親類・会社の人事部や同僚・友人から故人の財産状況などを聞きだすこともできます(連帯保証人の地位は相続されますので、会社経営者の方は気を付ける必要があります)。
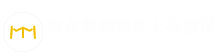
 トップページ
トップページ お問合せ
お問合せ 詳しくはこちら(相続と税金)
詳しくはこちら(相続と税金) 税務調査
税務調査